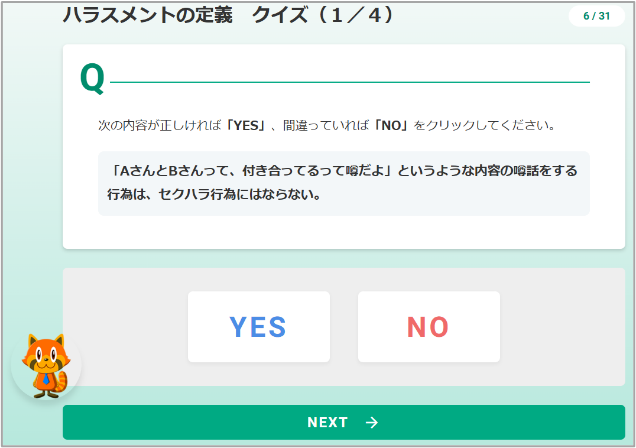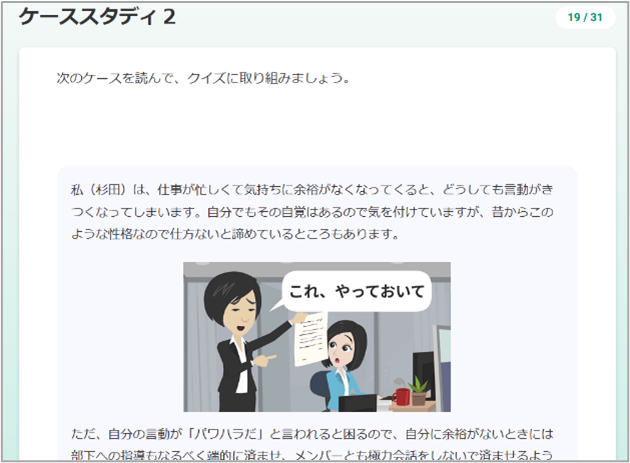ハラスメント防止研修を“毎年やるだけ”にしないために ― 飽きないeラーニング教材の工夫
企業にはハラスメント防止措置が義務付けられているため、その一環として、ハラスメント防止教育を毎年必須で実施している企業は少なくありません。
しかし、年に一度の研修だからと、毎年同じ教材や講義で研修していると、「もう内容は知っている」「毎年同じだから退屈」と感じる受講者が増え、せっかくの教育機会が形骸化し、貴重な時間が無駄になりかねません。
例えば、1人あたり15分のeラーニング研修だとしても、100人が「なんとなく見ただけ」で終われば 15分×100人=1,500分(25時間)の稼働を無駄にしたのと同じことに。これは組織にとって大きな損失です。
そこで本稿では「飽きずに、効果的に学べるeラーニング教材」のポイントを考えてみます。
毎年実施するからこそ「飽き対策」が重要
- ハラスメント防止教育は、繰り返しの学びが大切。
- ただし同じ内容・同じ表現では「またこれか」という気持ちが強くなり、受講者が主体的に学ばなくなる。
- 「飽きさせない工夫」は、教育効果を左右する最も大事な要素のひとつ。本記事では3つの工夫を具体的に紹介。
- 工夫1:内容を常にアップデートする
- 工夫2:表現方法の工夫で引き込む
- 工夫3:研修内容を「自分ごと」にしやすい仕掛け
工夫1:内容を常にアップデートする
最新の法改正情報や社会的ニュース(判例や話題の事例)を押さえていると、eラーニングで学習することへの「納得感」が高まります。
ハラスメント関連の法律はこれまでも何度か改正されており、直近では2025年6月に労働施策総合推進法の改正法が公布され、2026年中の施行が予定されています。こうした最新情報を押さえていない教材だと、せっかくの教育機会が「最新の知識・認識の共有」の場とならないリスクもあります。
工夫2:表現方法の工夫で引き込む
eラーニングと聞いて、一方的なナレーションや、紙芝居のようなスライドだけの教材をイメージした方もいるかもしれませんが、こうしたタイプのeラーニングは、受講者にとって学習の負担感が大きく、集中して受講しづらい教材です。
クイズ形式の解説、アニメーション動画や会話形式のケーススタディ、シミュレーションタイプの教材など、eラーニングは多様な表現方法を取り入れることが可能です。eラーニング教材の採用を検討する際には、内容チェックはもちろんのこと、「飽きずに取り組めるよう、表現の工夫がされているか」という点もぜひチェックいただきたいポイントなのです。
工夫3:研修内容を「自分ごと」にしやすい仕掛け
ハラスメント防止研修の目的は、受講者の知識や認識を深め、組織で起こるハラスメントを予防・減少させることでしょう。そのために、社内研修の内容を「自分に関係のあること=自分ごと」として捉えてもらうことが重要です。
自分ごととして捉えてもらうために効果的なのが、一部でもよいので、自社のオリジナルコンテンツを教材に載せることです。一例をあげると、以下のような方法があります。
- 教材の冒頭に、「ハラスメント防止」についてのトップメッセージを掲載する
- 自社で実際に起きた事例(ヒヤリハットを含む)で、クイズの設問や選択肢を作成する
- 社内に掲示しているポスターや配布物などを教材内でも示す
- ハラスメントの相談窓口情報について、より詳しい情報を周知する
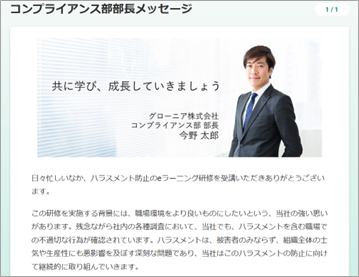
当社は「飽きずに受けていただけるeラーニング」のご提供で、ハラスメント防止をご支援します
本稿では、「飽きずに、効果的に学べるeラーニング教材」のポイントをご紹介しました。以上の3つの工夫を意識することで、毎年の研修を“やるだけ”ではなく、組織の成長につながる教育の場にすることができます。
当社はその実現を「飽きずに受けていただけるeラーニング」の提供でご支援しています。当社がご提供するLMS、GRONIA plusの「ハラスメント防止シリーズ」は、こうしたポイントを押さえた教材をご提供しています。その背景には、受講者に前向きに取り組んでいただける教材で、限られた学習時間での学習効果をできる限り高めたいという、制作チームの思いがあります。
よろしければぜひ一度、教材サンプルをご覧ください。また、eラーニング教材に関する疑問やお悩みも、ぜひお気軽にお寄せください。