心理的安全性とハラスメント防止 ― eラーニングで始める職場づくりの基本
ハラスメント防止教育を行う企業の中で、近年「心理的安全性(psychological safety)」をテーマにしたeラーニング研修を実施するケースが増えています。
ビジネスの現場でいわれる「心理的安全性」とは、チーム内でメンバーが他者に対して「率直であることが許されるという感覚を持てること」を意味します。心理的安全性の確保された職場では、失敗や意見の違いを伝えても非難されず、互いに尊重し合いながら、成果を出すことができます。
この“安心して仕事ができる職場環境かどうか”は、ハラスメント防止と深く関係しています。なぜなら、心理的安全性が低い職場では、不適切な発言や行為を見ても誰も注意できず、問題が放置されやすくなるからです。

本稿では「心理的安全性とハラスメント防止」について考えてみます。
心理的安全性とハラスメント防止
- 心理的安全性が高い職場は、注意し合える職場
- 「直接介入」はハラスメント防止の有効な一歩
心理的安全性が高い職場は、注意し合える職場
ハラスメントを防ぐことが難しい理由のひとつに、「ハラスメントの加害者は、自分の言動がハラスメントとなっていることに気づきにくい」ということがあります。加えて、特にパワハラは無意識のうちに行為がエスカレートしやすいという特徴もあるため、「周囲の見て見ぬふり」によってハラスメント行為は悪化していきます。
一方、心理的安全性のある職場では、次のような行動が自然に起こります。
-
- 不適切な言動を見かけたら、その場で自然に注意できる
- 注意された側も、反発ではなく「気づきを得る」形で受け止められる
- 相談や報告がしやすく、早期に問題を解決できる
つまり、「注意できる」「受け止められる」環境こそが、ハラスメントを未然に防ぐ土台になるのです。
「直接介入」はハラスメント防止の有効な一歩
ハラスメントが疑われるような不適切な言動を受けたり、見聞きしたりしたときに、その場で行為者に声をかけることを「直接介入」といいます。これは、ハラスメント防止の考え方として知られるアクティブ・バイスタンダー(行動する傍観者)の「5つのD」のひとつにも含まれています。
アクティブ・バイスタンダーの5つのD:
1. 注意をそらす、2. 直接介入する、3. 第三者に助けを求める、
4. あとでフォローする、5. 証拠を残す
詳しくはこちらもチェック!
「Direct(直接介入)」を行うには、声を上げても大丈夫だと思える心理的な安全が不可欠です。そして、心理的安全性が高い職場ほど、注意の言葉が受け入れられ、行動の改善が起こりやすくなります。
心理的安全性を理解し、育むためのeラーニング活用
心理的安全性を高めるには、まずその概念と必要性について共通認識を持つことが欠かせません。しかし、抽象的なテーマでもあるため、全社員に同じレベルで浸透させるには工夫が必要です。
その点、eラーニングは理解促進の第一歩として非常に有効です。
- 社員が自分のペースで学べる
- 具体的な事例やアニメーションでイメージしやすい
- 限られた時間のなかで、他のハラスメント防止教育などと組み合わせて実施が可能
といった特長を生かして、「心理的安全性とは何か」「自分の言動がどう影響するのか」を誰もが学べる環境を作れます。
ハラスメント防止シリーズを提供している当社では、ハラスメント防止やメンタルヘルスという観点を持ちながら心理的安全性について学習できるeラーニング教材をご用意しています。
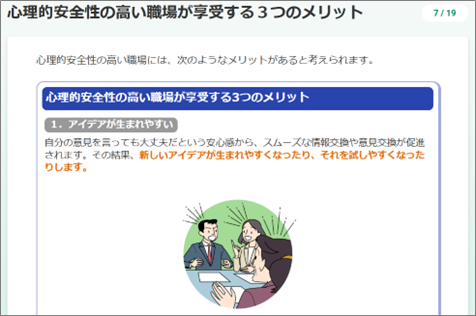
よろしければぜひ一度、教材サンプルをご覧ください。また、eラーニング教材に関する疑問やお悩みも、ぜひお気軽にお寄せください。


